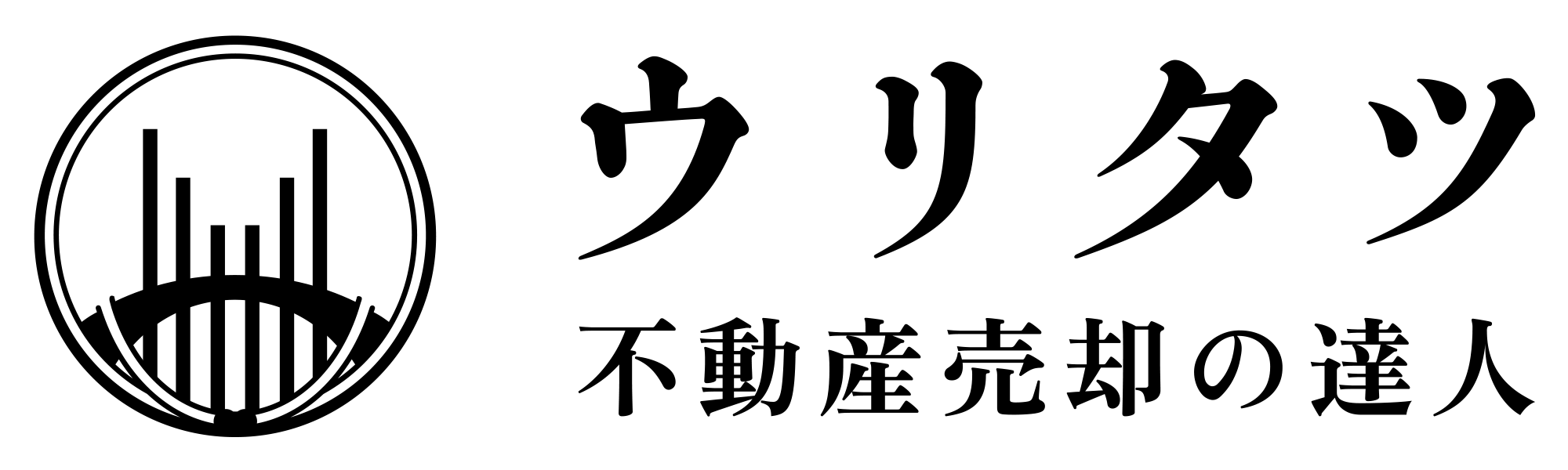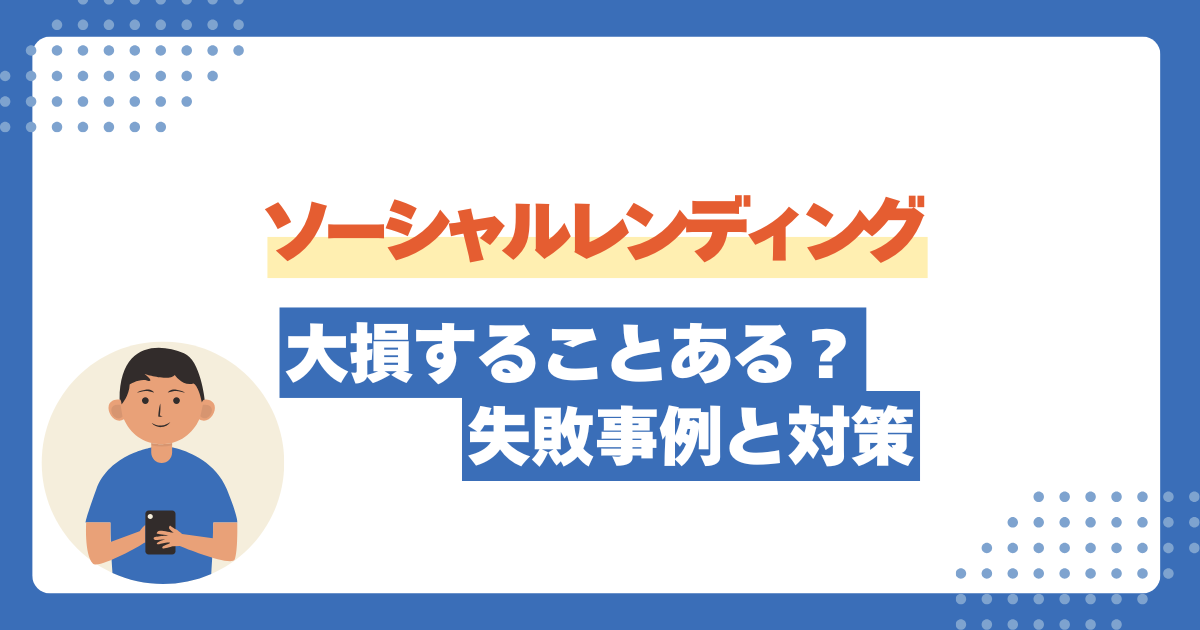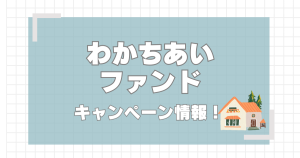「ソーシャルレンディングは大損することもあるのか?」
「ソーシャルレンディングのリスクを知るために大損の事例を知りたい」
このような投資家は多いことでしょう。
投資に「ノーリスク」はありません。ソーシャルレンディングにも一定のリスクはあります。
本記事では、ソーシャルレンディングで大損した事例と、リスクを抑えるための対策を紹介します。
上場企業などを中心に貸付をするソーシャルレンディング「Fundsが新規口座開設の特大キャンペーンを実施中です!
口座開設と出資で、最大4,000円の現金がキャッシュバックされます。

口座開設だけでも1,500円がもらえるのは、かなりのお得なキャンペーンですね。
キャンペーンは予告なく終了することがあるので、興味がある方は必ず公式サイトで最新情報をチェックの上、このタイミングでぜひ登録を進めてみてください。
ソーシャルレンディングにおいて「大損」はある?
ソーシャルレンディングは融資を受けたい企業や個人と、個人投資家をオンライン上でつなげる投資サービスです。
投資家目線では、少額からほったらかしで投資でき、高利回りも狙えます。
企業・個人目線としては、金融機関以外からも資金調達ができるなどのメリットもあるため、利用する企業や個人は増えています。
一方で、投資先の事業失敗や運営会社の不正など、大損につながるリスクもあります。
ここでは、ソーシャルレンディングの大損事例として以下3点を紹介します。
- みんなのクレジット事件
- ラッキーバンク事件
- SBIソーシャルレンディング事件
ソーシャルレンディングの大損事例1.みんなのクレジット事件
みんなのクレジット事件とは、年利換算で最大14.5%の高利回りを謳って投資家から集めた40億円のうち、30億円の償還が滞った事件です。
結局30億円は、約9,600万円で債権回収会社に譲渡されたので、29億円の損失となり、投資家が集団訴訟を起こしました。
問題点としては、以下のような点が挙げられます。
- 融資先を明記しなくてもよいことから自社の関連会社に融資していた
- 集めた出資金をキャンペーンのために利用するなど、ずさんな運用をしていた
- 担保の説明が不十分だった
つまり、集めたお金を真面目に運用せず、自社の関連会社の運営資金に回すなどして、結果的に損失を出しました。
順調に出資金が集まっても、運用会社がいい加減だと損失が出る事例です。
ソーシャルレンディングの大損事例2.ラッキーバンク事件
ラッキーバンクは、「全案件不動産担保付き・年利10%」というキャッチコピーで人気を集めた「ラッキーバンク」が、2度にわたって行政処分を受け、最終的にサービス停止にまで至った事例です。
最終的にラッキーバンクは二度の行政処分を受け、45億円以上の償還遅延をだし、業務を停止しました。
問題点としては、以下のような点が挙げられます。
- 多くの資金を実質的な関係会社に融資
- 担保不動産の評価が過大(査定額に信頼性なし)
- 金融庁から2度の行政処分を受け、事業停止へ
現在もホームページは残っていますが、ファンドの運用も新規投資家の募集も行っていません。
「全案件不動産担保付き」であっても、必ずしも安心とは限らない事例です。
ソーシャルレンディングの大損事例3.SBIソーシャルレンディング事件
SBIソーシャルレンディング事件とは、SBIホールディングスの子会社であるソーシャルレンディング会社が、度重なる不祥事を理由に金融庁から指導を受け、最終的に自主廃業した事件です。
問題点としては、以下のような点が挙げられます。
- 融資先企業(うち一社が太陽光開発業者)による使途不明金の発覚
- 金融庁からの業務改善命令
- これを受けて自主廃業へ
先に紹介した2つの事例とは異なり、親会社のSBIホールディングスが出資者たちの出資金の元本を償還しました。
この事例では投資家の損失は出ませんでしたが、大会社の子会社であっても運用会社の経営が危うくなる可能性はあります。
どのような会社であっても、定期的に運用状態をチェックしましょう。
ソーシャルレンディングで大損する理由は?
ここでは、ソーシャルレンディングで大損する理由を2つ紹介します。
ソーシャルレンディングで大損する理由1.運営会社選びの失敗
ソーシャルレンディングは、まだ新しい投資方法です。
金融知識や運用経験のない企業も参入しており、規模の小さい会社でも始めることができます。
信頼性や実績、金融庁登録の有無など、しっかり確認することが重要です。
ソーシャルレンディングで大損する理由2.資金の集中投資
ソーシャルレンディングは高利回り案件も多く存在します。
そのため、高利回りに惹かれ1つのファンドに多額の資金を集中させてしまうこともあるでしょう。
利回りが良いファンドだとつい多めの投資をしたくなりますが、リスクを考えて複数の会社に分散投資をするなど、工夫が必要です。
大損しないために!3つの対策
ここでは、ソーシャルレンディングで大損しないための対策として以下の3つを紹介します。
- 運営会社を慎重に選ぶ
- ファンドの内容を確認
- 出資金を調整する
対策1.運営会社を慎重に選ぶ
ソーシャルレンディングにおいて、元本割れなどは複数起きていますが、大きな事件を起こしているのは、運用会社が大半です。
運用会社を選ぶ際は、実績や資金力、口コミを確認しましょう。
また、金融庁の登録有無の確認は必須です。
新規業者でも良質な業者はいますが、初心者は実績ある業者のほうがおすすめです。
対策2.ファンドの中身を確認
利回りが高いファンドは魅力ですが、ソーシャルレンディングサービスは、融資したお金の使い道や、融資先はオープンにすることが必須ではありません。
運営上、しかたない部分もありますが、融資先の情報は開示されている方が安心です。
サービスによっては融資先企業名・資金の用途までしっかり記載されているため、そういったファンドを選ぶことをお勧めします。
対策3.出資金を調整する
投資は分散が重要です。
1ファンドや1サービスに多額の資金を集中してしまうのは危険です。
できるだけ複数のファンドに少額から投資しましょう。
また、別のサービス会社でも同じ融資先に投資してしまっては分散にはなりません。
融資先は見えづらいため、よく確認しましょう。
おすすめのソーシャルレンディングサービス|Funds(ファンズ)

Funds(ファンズ)は、1円から投資できるソーシャルレンディングサービスです。
運営会社であるファンズ株式会社の出資会社には、三井住友信託銀行株式会社、日本郵政キャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、SV-FINTECH Fund、伊藤忠商事株式会社など一流企業が名を連ねています。
Fundsの大きな特徴は上場企業などに間接的に投資できることです。
多くのソーシャルレンディングは未上場企業への貸付がメインですが、Fundsは多くの案件が上場企業を対象にしています。
上場企業は未上場企業に比べ倒産リスクが低いため、比較的安全性の高い投資ができるでしょう。
なお、2019年1月23日〜2025年12月31日までの正常償還率は100%です。
※将来の運用成果等を保証するものではありません。
Fundsのキャンペーン情報

Fundsでは口座開設で現金1,000円がもらえるキャンペーンを実施中です!
| 特典 | 最大5,000円の現金 |
| 内容 | ①新規口座開設をした方に、投資に使える現金1,000円をプレゼント ②口座開設後2026年1月31日までの投資額に応じて、投資に使える現金最大4,000円プレゼント |
| 条件詳細 | ①キャンペーン期間中に新規口座開設申請をして、2026年2月4日までに口座開設を完了させる ②口座開設完了後、2026年1月31日までに1万円以上投資する 1万円以上:1,000円 50万円以上:2,000円 100万円以上:4,000円 |
| 期間 | 2025年12月1日から2026年1月31日23:59まで |
| 配布方法・配布時期 | ①口座開設完了の1週間後 ②2026年2月末 |
| 注意点 | ※口座開設の申込みから手続き完了までには、審査等により、通常1〜5営業日程度時間がかかる |

まとめ
本記事では、ソーシャルレンディングの大損事例について解説しました。
ソーシャルレンディングは投資のため、どうしても一定のリスクはあります。
さらに、運用会社の放漫経営でサービスが終了する恐れもあるでしょう。
ソーシャルレンディングを行う場合は、ファンドだけでなく運用会社もしっかりと実績を確認したうえで、運用会社やファンドを選びましょう。
また、一か所の運営会社に多額の資金を投資しないのも1つの方法です。